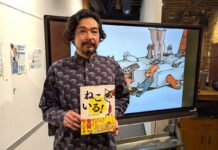北米で初めてとなる「北米国際よさこい祭り」が9月27日と28日の2日間、アルバータ州レスブリッジ市の日加友好日本庭園で開催された。日本、カナダ、アメリカのチームから踊り子とボランティア約200人が集結、訪れた約2,000人の観客を魅了した。
イベントを主催した楓文化協会の本田朋之さん、田中恵美子さん、井上昇さんに話を聞いた。
日加3人の情熱が動かした初開催

イベントの発端は3人の共通した「日本文化を自らの手で伝えたい」という思いだった。
本田さんは、愛知県出身でアルバータ州カルガリー市に移住後、日本では当たり前にある地域の祭りや季節の行事がほとんどないことに気づいたという。日本人の人口は増えているのに、日本の祭りが増えていない。
そこで2017年にカルガリーでよさこいチームを立ち上げた。その後、地元のパレード「カルガリー・スタンピード」への参加を続ける中で、2023年ごろから「自分たちでよさこいの祭りを開きたい」という構想が本格的に芽生えた。レスブリッジ市の日加友好日本庭園を訪れた時、「ここでよさこいができたらおもしろい」と直感し、開催の可能性を関係者に相談したという。
しかし当時、本田さんには自身が所属するカルガリーのチーム以外につながりがなく、実現は容易ではなかった。そんな中、よさこいメンバーに紹介してもらい出会ったのが高知県よさこいアンバサダーとして、オンタリオ州トロントを中心に海外や日本で活動する田中さん。田中さんは「海外でよさこいは30カ国以上に広がってはいますが、まだまだその間の壁は大きい。お互いをつなげるきっかけにしたいと思いました」と語る。
当初は迷いもあった。「お会いしたことがなかったので」と正直に振り返る。それでも「子どもたちの未来のために何かを残したい」という本田さんの言葉に心を動かされ、一緒にやろう、と決意した。
さらに、田中さんの紹介で日本から井上さんが加わった。本場の高知や東京で18歳から30年以上よさこいに携わる井上さんにとっても、北米での開催は未知の挑戦だった。「最初に話を聞いたときは、正直ハードルが高いと思いました」。それでも「本田さんの情熱に圧倒された」と語り、「日本では考えられないスピード感で動き、地元の理解を得ていく姿を見て、これは本当に実現するかもしれないと思うようになった」と話した。
こうして日本、カルガリー、トロントの3拠点がつながり、準備は本格的に動き出した。
「歴史を一緒に作りたい」
しかし、前例のない試みは困難の連続だった。スポンサー探し、助成金申請、チーム集め。資料も実績もない中での説得は容易ではない。本田さんは「見せられるものがない状態で賛同を得るのは大変だった」と本音を漏らす。田中さんは「一番難しかったのは日本のチームで、実際に旅費を伝えた時に高額だったので、そこの壁を感じた」と説明した。
それでも3人は、北米で初めてのよさこい祭りを開催するという歴史を一緒に作りたいと訴え続けた。その姿勢が支援者の共感を呼び、よさこい発祥の地である高知県で、1954年に結成された最古のよさこいチーム「帯屋町筋」が協力したことが大きな転機となった。その後日本各地や北米のチームにも参加の輪が広がった。
本田さんは「日系コミュニティの発展を含め、自分たちで作るということがすごく重要だと思った」と語り、北米で文化を自らの手で形にする意義を強調した。
北米で芽生えた新しい文化の輪
鳴子の音が響き、祭りの始まりを告げた。開会パレードでは、色とりどりの衣装をまとった踊り子たちが庭園を進み、観客の拍手が会場に広がった。来場者は約2,000人、踊り子とボランティアを合わせ約200人。北米や日本各地から集まった人々が、言葉や文化の違いを越えて一体となった。

本田さんは全体統括として会場を駆け回っていた。「当日は本当に走り回っていました。Tシャツが届かない、スピーカーの準備ができていないといったトラブルも多かったけれど、みんなが笑顔で楽しんでくれた。それだけでうれしかった」と笑顔で振り返る。
開催前日に、予約していた大型バス2台から日本チームの踊り子約80人が降り立った瞬間を今でも忘れられないという。「150人来るとは聞いていたけれど、実際に目の前で降りてきた時は震えました。ああ、本当にこの日が来たんだなって実感しました」と目を細めた。

司会を務めた田中さんは、観客と踊り子の笑顔があふれる会場の雰囲気を印象深く覚えている。「高知の帯屋町筋のチームの方が『何も考えず純粋にこんなによさこいを楽しめたのは久しぶりだった』と言ってくださって、とてもうれしかった」。異なる文化や背景を持つ人々が鳴子を手に一体となって踊る姿は、主催者や観客、全ての参加者の心に残った。
井上さんも「余韻がすごくて、単に幸せだったなというところに行きつく」と語り、「北米という縁もゆかりもない土地で、自分と同じ思いを持つ人たちと出会えた幸せを強烈に感じました」と続けた。

また、会場ではワークショップや共同パフォーマンスも行われ、日本チームと北米チームが一緒に作品を踊る場面もあった。田中さんは「よさこいは子どもから大人まで鳴子を握れば誰でもできるところ、そして言語や育った背景に関係なく踊れるところが一番の魅力」と語り、「だからこそ現在世界30カ国以上に広まっているんだと思います」。
「続けていくことで初めて文化になる」

初開催を終えた今、3人はすでに次の目標を見据えている。アンケートでは「また来たい」という声が9割を超え、予想を上回る反響が寄せられた。イベントを終えてなお、会場で芽生えたつながりが広がり続けており、この流れを絶やさずに次へつなげたいという思いが3人を再び動かしている。
井上さんは、現地での経験を通して感じた変化を語る。「日本にいると当たり前のことが、外に出ると当たり前ではないと気づきます。そうした経験を通じて、日本の人たちにも新しい視点で文化を見つめ直してほしい」と話し、よさこいを広めるだけでなく文化のあり方を見直す契機にもなったという。
田中さんも「文化は子どもたちに伝えていかないと消滅してしまう。未来につないでいけるようなお祭りにしていきたい」と強調する。「(イベント名に)国際という言葉を入れたのは、北米だけでなく世界中の人に参加してほしいという願いから。将来的にはヨーロッパやアジアからもチームが集まるお祭りにしたい」と展望を語った。
2回目の開催は2026年秋に予定されている。本田さんは「日本では当たり前にあるお祭りも、ここカナダでは誰かが動かないと始まらない。待っているだけでは何も生まれない」と語り、「北米にいる日本人一人ひとりが、自分の得意なことを生かして動き出せば、日系コミュニティはもっと豊かになる」と呼びかけた。
2026年の開催について、詳細については以下のウェブサイトから。https://kokuyosa.com/





(取材 田上麻里亜)
合わせて読みたい関連記事