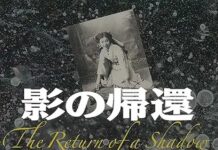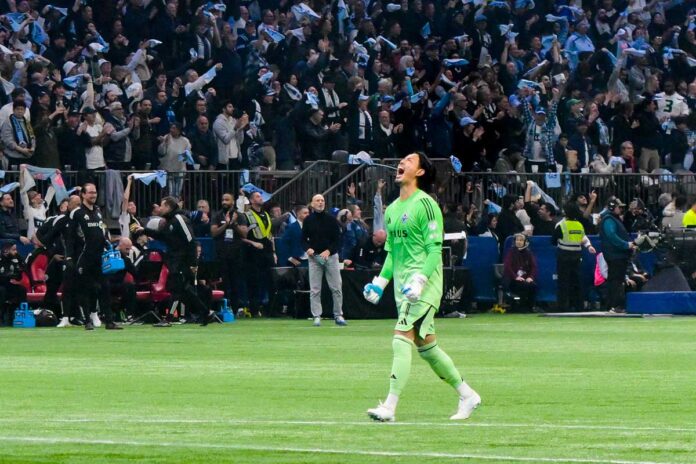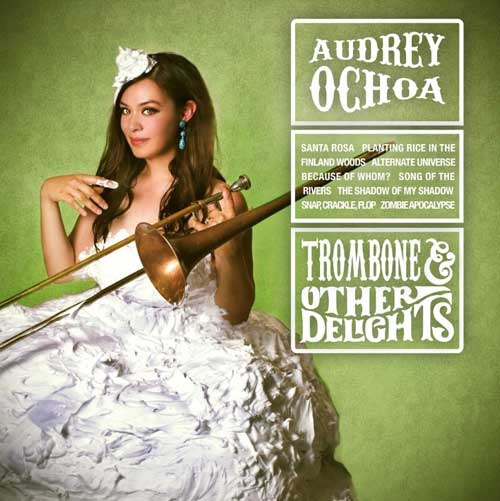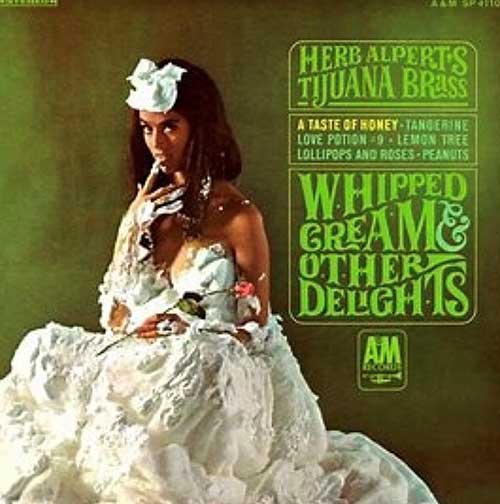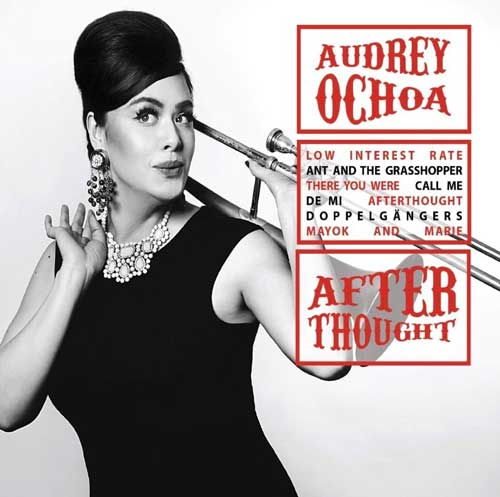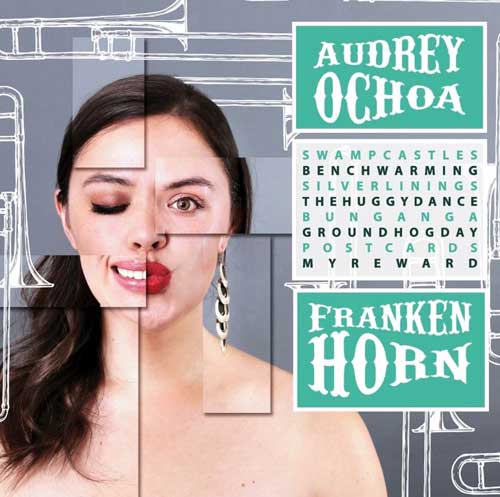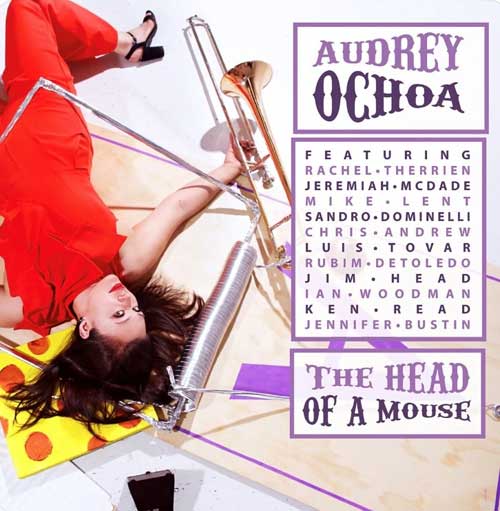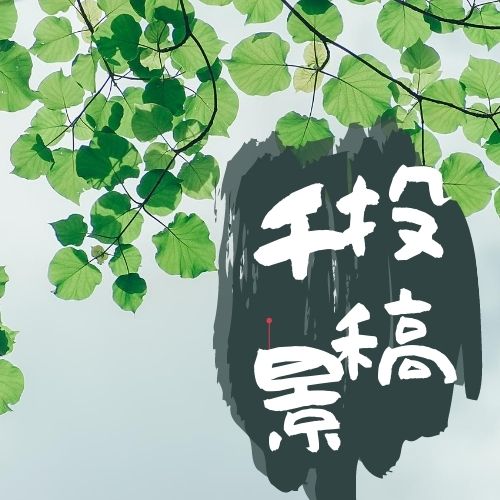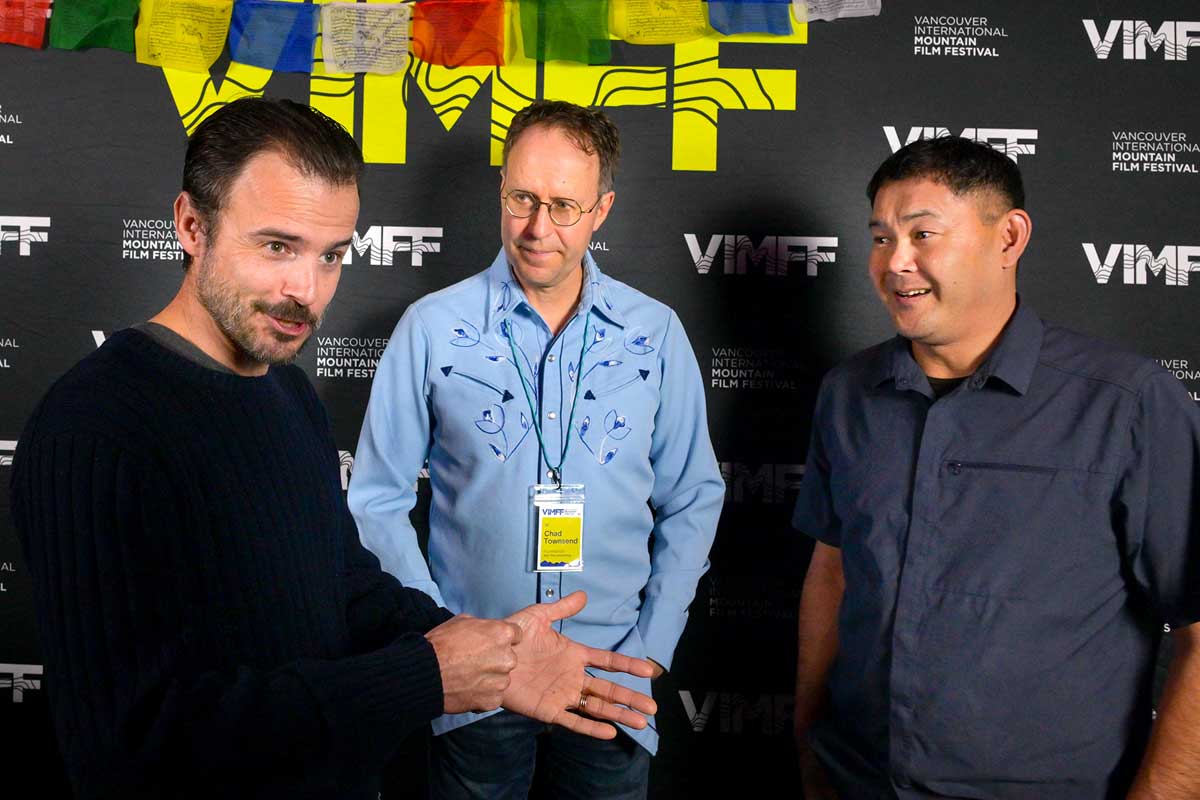年末の催し
日系文化会館:
日本マーケットとホリデーコンサート:12月13日(土)12:00₋16:00、ジャパンブティック、焼き菓子、書籍、Atelier Tsubaki、Boutique Meico、Koto-an Wagashi、Mofleema made in Canada、SA Design、Sakao Entreprises、Tokusen、Wabisabijazzの商品、カフェテリアでのラーメン、運がよければ賞金675㌦の50/50のラッフルなど、全て現金販売、バッグご持参でお出かけください。このほかにonline holiday auctionが12月6日‐14日に行われます。
www.jcccm-cccjm.ca/wp-content/uploads/2013/10/unnamed-1.jpg
Online Auction:https://www.32auctions.com/jcccm?fbclid=IwY2xjawOHF3RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2SlRSdkhpczViNzcxSTdYc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MghjYWxsc2l0ZQEyAAEeiMO8owwrPQUWLt08430C21-q4VcSjRUFD20WLX6GZjEsRRSfGaF_NzbAX_I_aem_XErbZaN0FsRGphGaLdeIGA
MARCHÉ À LA JAPONAISE(日本のホリデーマーケット):11月22・23日12:00‐16:00、1700 Atateken Montréal、緑茶、日本の食材、和菓子、着物、アクセサリーなど、約20店舗の出店。www.facebook.com/marchejaponaismtl?locale=fr_FR
LE JAPON SOUS LE SAPIN:12月12‐14日11:00‐17:00、Patro Villeray, 7355 ave. Christophe Colomb, Montreal:新規に始まったホリデーマーケット、日本酒、和風調味料、陶器、盆栽、書道、和雑貨の出店。
一般のクリスマスマーケット:https://www.mtl.org/en/experience/shop-christmas-markets-montreal
GREAT CHRISTMAS MARKET:11月21日‐1月4日、Quartier des spectacles、Ste-Catherine通り、BalmoralとJeanne-Manceの間です。https://noelmontreal.ca/grandmarchedenoel/en/the-great-christmas-market/
SALON DES MÉTIERS D’ART DU QUÉBEC À MONTRÉAL:アーティザンによるさまざまなギフト用の作品などの展示即売:12月11日‐21日 Palais des Congrès de Montréal 、l1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle https://www.metiersdart.ca/
大晦日の行事
モントリオールでの2025年大晦日の行事:オールドポートでの花火のほかに、カシノ、市内のホテルなどで、さまざまなイベントがありますが、既に前売り券が売り切れの行事もあります。www.montrealnewyearseve.com/
モントリオール近辺での日本人/日系カナダ人関連の催し物など
巡回展「構造環境:もうひとつの日本ガイド」:日本に現存する建築・土木・ランドスケープなど80点の写真、テキスト、映像での紹介展示。2026年1月25日まで。Centre de design de l’UQAM, 1440 rue Sanguinet, https://centrededesign.com
モントリオール植物園: Montreal Botanical Garden, 4101 Sherbrooke E. https://espacepourlavie.ca/en/botanical-garden
冬の間は園内でスキーが楽しめます。
IKEBANA INTERNATIONAL MONTREAL CHAPTER: 12月、1月はZOOMでの会合のみ。連絡先:田中和子 kazuko.dorangeville@gmail.com
RIVES-YUKI ISAMI:五老海幸(フルート)コンサート、
・2026年2月8日(木)19 :30、Maison de la culture Maisonneuve 4200, rue Ontario Est, Montreal https://montreal.ca/evenements/rives-yuki-isami-90554
・2026年3月28日(土)14 :00, Maison de la culture Mrie-Uguay, 6052 boul. Monk, 2階、https://montreal.ca/evenements/rives-yuki-isami-89135
・2026年4月4日(土)19 :00, Le centre communautaire Victoria Hall, 4626 Rue Sherbrooke O, Westmount
その他の催し
モントリオール日系文化会館、8155, rue Rousselot, Montreal, H2E 1Z7
地下鉄:Jarry下車、バス197 E.
電話:514-728-1996、514-728-5580
www.jcccm-cccjm.ca/?language=en
www.facebook.com/jcccmcccjm/
(jcccm_yh@bellnet.ca)
(日系文化会館のニュースの引用についてはスーザン・レベックの了解を得ています。)
<図書館>
開館時間:日曜日・水曜日13:00 – 16:00 、木曜日10:30 -14:30、一度に借りられる冊数が10冊に。会館入口に売本コーナー(1冊$1、現金のみ)。
<KAIWA⁻ランゲージエクスチェンジ>:毎月の第2、第4日曜日(祝日のある週末以外)、13:30‐15:30。要会員登録 www.jcccm-cccjm.ca/?language=en
<シニア・ドロップイン>:‐月に2回開催。要予約、ランチ代$10、参加予約必須。予約は開催3日前までに。
クリスマス・ランチ: 12月18日(木)10:30-14:00
申込先:reiko_leojp@yahoo.co.jp または514-728-1996まで。
<チームオレンジ>:連絡先:mnishi_jamsnetcanada@gmeil.com
<和菓子作りボランティア募集>: 上記のドロップインカフェでのボランティアに参加できる方、月に1~2度の予定。 連絡先:jcccm_yh@bellnet.ca
<遠藤さんの手作り納豆・味噌・大豆の販売>(会員限定):納豆(200g $4)、手作り味噌($6)、小粒大豆($8/2kg)、現金支払い、詳細:514-728-1996
<子どもクラブ>:各自弁当持参、参加費$1、問合せ:kodomoclub.montreal@gmail.com
・日系文化会館会員への会員優待プログラム:当館会員限定の割引サービスを提供してくださっている日系企業をサポートするために、この特典をぜひご利用ください。有効会員証を提示するだけで利用できます。サービスをご提供くださるのは、Beauté Business, Brasserie San-O(Promo code「JCCCM10」₋パントリー製品10%割引)、 Kokoro Care Packages, Kyoto Fleurs, Misa Oku, Myofu-an Dojo, Thés Guru, Tokusen Store, Yen cuisine japonaise, Charyu, MTL Shamisen Project, Yamato Karate Academyの各企業です。
トロント
JCCCトロント: 6 Sakura Way, Toronto, ON, M3C 1Z5
KEEP LANTERN LIT:12月6日17:30 https://jccc.on.ca/event/2025/12/keep-lantern-lit-2025
作って学ぶ大みそか:12月30日12:00‐20:00 https://jccc.on.ca/event/2025/12/omisoka-workshops-2025
JSS(ジャパニーズソーシャルサービス):会員登録をすると、オンラインでの講座などにも参加できます。https://jss.ca/en/
国際交流基金トロント日本文化センター:E-libraryで日本の本、マンガや雑誌などを読めます。https://jf.overdrive.com/https://tr.jpf.go.jp/
ケベック市
日本ケベック友好協会:www.facebook.com/associationdamitiequebecJapon/
・ランゲージ・エクスチェンジ(仏語-日本語):ラヴァル大学院生が主催するオンライン・ランゲージ・エクスチェンジが、毎週土曜日朝8時(カナダ東部時間)から開催されています。www.meetup.com/en-AU/canasian-station/
問い合せ先:Pascal Paradis pascal.paradis.2@ulaval.ca
オタワ市
CHRISTMAS CONCERT:12 月6日、Southminster United Church, 15 Aylmer Ave, Ottawa https://www.ca.emb-japan.go.jp/2025_shared_images/Christmas-Concert-Imai-Yamada.png
もちつき:12月7日12:00-17:00、Preston Event Centre, 523 St Anthony St.Ottawa https://ojca.ca/ja/2025/11/08/%e3%82%82%e3%81%a1%e3%81%a4%e3%81%8d2025/
一般のフェスティバル
モントリオール
LUMINO:11月6日-8日、ダウンタウンのSte-Catherine WとQuartier des spectacles周辺にさまざまな照明が施されます。https://lagrandedegustation.com/
FESTIVAL INTERNATIONAL BACH MONTRÉAL : 恒例のバッハ国際音楽祭。12月10日まで。https://festivalbachmontreal.com/?gad_source=1&gad_campaignid=22687374449&gclid=Cj0KCQjw_rPGBhCbARIsABjq9cco6M733lELh1Xjy9o8TyF4AzidwrOR5ORRret0ZABH79a0fsZDgp8aAorwEALw_wcB
IGLOOFEST:2026年1月15日‐2月7日、オールドポート周辺での歌や踊りの冬の祭典。https://igloofest.ca/en
トロント
21C MUSIC FESTIVAL:1月16日‐5月8日、21世紀音楽祭。www.rcmusic.com/performance/21c-music
オタワ
WINTERLUDE:11月4日、22日、29日、2026年2月14日、3月6日、3月25日 www.chamberfest.com/series/2025/concert-series-2025-26/
展覧会・展示
MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS:www.mbam.qc.ca/en/(MMFA)
Decorative arts, design pavilionでの展示再開
-MOMENTAxMBAM:2026年2月1日まで。
-KENT MONKMAN:History is Painted by the Victors:2026年3月8日まで。
-MARIE-CLAIRS BLAIS: Streaming Light:2026年1月4日まで。
-Kurt Henschläger: EVER MORE:2026年4月5日まで。
-Comfort and Indifference Recent: Acquisitions by MAC:2026年5月3日まで。
-From the Functional to the Fabulous: 6 0Years of Decorative arts and Design、2026年9月13日まで。
-Rising Suns: art from the Confederacies of the Great Lakes and Rivers:2026年10月11日まで。
‐美術館アクティビティ サイト:www.mbam.qc.ca/en/calendar/?filters=7
MAC:Musée d’art Conemplain de Montréal http://macm.org/ (改装中)展示はPVM, Place Ville Marieで。
-In Praise of the Missing Image:2026年3月8日まで。
‐Graphic Worlds:Outdoor mural:2026年1月31日まで。
-Online Workshops:https://macm.org/quoi-faire-au-mac/#activites
MCCORD STEWART MUSEUM:https://www.musee-mccord-stewart.ca/fr/expositions/
-Africa Fashion:2026年2月1日まで。
-Aunties Work-The Power of Care:2026年5月24日まで。
MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal : https://pacmusee.qc.ca/en/
-Alley-oop₋An Interactive Adventure:2026年1月11日まで。
-Montréal Night Life, 2026年2月15日まで。
PHI FOUNDATION FOR CONTEMPORARY ART:https://phi.ca/en/
-Josèfs Ntjam :Swell of Spæc(i)es:2026年1月1日まで。
-Manuel Mathieu: Unity in Darkness:2026年3月8日まで。
-Keiken: Sensory Oversoul, 2026年3月8日まで。
市外
NATIONAL GALLERY OF CANADA:www.gallery.ca/ NGC、オタワ
–WINTER COUNTS: EMBRACING THE COLD:2026年3月22日まで。
-THE GOVERNOR GENERAL’S AWARD IN VISUAL AND MEDIA ARTS 2025:12月4日‐2026年5月3日まで。
-SYLVIA SAFDIS: TERRE:12月12日‐2026年10月25日まで。
-CAMERA AND THE CITY:12月12日‐2026年3月15日
–IN RELIEF: THE WORK OF DORA DE PÉDENY-HUNT(1913-2008):2026年4月12日まで。
–THINGS WHICH ARE PER SE CONTINUOUS: THE MICHAEL NESBIT COLLECTION, WINNIPEG:12月14日まで。
-PUCKER UP! The Lipstick Prints of Joyce Wieland:11月26日まで。
-FOCUS SERIES:2026年6月まで。
-JIN-ME YOON: HONOURING A LONG:2026年3月まで。
OTTAWA ART GALLERY:オタワ OAG https://oaggao.ca/whats-on/
-HALLWAYS OF HOPE:2026年1月11日まで。
-ART OF GOOD DEATH:2026年1月11日まで。
-ART PARCEL: A HOLIDAY SALE;2026年1月18日まで。
-GROTTO:2026年2月8日まで。
-CHAOS BLOOM-TIDAL WAVE:2026年6月6日まで。
-VISIONS AND VIEWS : LANDSCAPE AND VIEWS IN FIRESTONE COLLECTION OF CANADIAN ART:2026年1月11日まで。
ROM:www.rom.on.ca/en/ 、トロント
‐SAINTS, SINNERS, LOVERS And FOOLS-300 Years of Flemish Masterworks。2026年1月18日まで。
-WILD LIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2025:2026年3月まで。
-SHARKS:2026年3月まで。
オンライン展示
‐AFTERSHOCKS-Japanese Earthquake Prints:
‐The Burgess Shale, Bluewhale Discoveredなど。www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/aftershocks-japanese-earthquake-prints
ART GALLERY OF ONTARIO、トロント。https://ago.ca/exhibitions
-Yayoi Kusama’s Infinity Mirrored Room-LET’S SURVIVE FOREVER:2026年5月まで。
-Joyce Wieland:Heart On、2026年1月4日まで。
-Painted Presence: Rembrandt and his Peers:2026年2月1日まで。
-Naoko Matsubara:展示中
-Kazuo Nakamura:展示中
このほか多数の展示
JFT(Japan Foundation Toronto):https://tr.jpf.go.jp/
-HIROSHIMA APPEALS: A Poster Exhibition of Global Message:12月20日まで。
コンサート・パフォーマンス
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL:音楽監督 Rafael Payare,
www.osm.ca/fr/
www.osm.ca/en/season-25-26/
-THE MESSIAH: HALLELUJAH!:12月10日、11日19:30‐21:30、MSM
ORCHESTRE METROPOLITAIN:2025‐2026 Season
https://orchestremetropolitain.com/fr/concerts/sortileges-symphoniques/?show_date_id=9090
-L’ORATORIO DE NOEL:12月17日19:30、Basilique Notre-Dame de Montréal、110 Notre-Dame W. https://orchestremetropolitain.com/fr/concerts/loratorio-de-noel/?show_date_id=9175
ORHHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL:
-Händel’s Messaiah:12月11日、19:30、Crypt of Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal, SJO, 3800 Queen Mary Rd., $20-99 https://en.orchestre.ca/
BOURGIE CONCERT HALL:BCH www.mbam.qc.ca/en/bourgie-hall/
-Taurey Butler Trio 2025: A Charlie Brown Christmas:12月16日18:00、$22‐44www.mbam.qc.ca/en/activities/taurey-butler-trio-2025-a-charlie-brown-christmas-5/
GRANDS BALLETS CANADIENS https://grandsballets.com/en
(日本人ダンサー、石井杏奈、河野舞衣、菅原愉衣も出演)
-The Nutcracker, 12月12‐30日14:00、19:30、SWP、Place-des-Arts $197‐232
OPÉRA DE MONTRÉAL: www.operademontreal.com/en
Janáček’s Jenůfa :11月22日19 :30、27日19 :30、30日14 :00、SWP、$30‐154
https://operademontreal.com/en?gad_source=1&gad_campaignid=672193426
DANSE DANSE:https://www.dansedanse.ca/en
TANGENTE DANSE: https://tangentedanse.ca/
CENTAUR THEATRE: https://centaurtheatre.com/prices-subscriptions/
CENTRE SEGAL : www.segalcentre.org/en/hom
市外
オタワ
NAC‐National Art Centre https://nac-cna.ca/en/season、オタワ
-The Nutcracker : Royal Winnipeg BalletとNAC Orchestraによる公演。12月3日‐7日、12:30、12月6日、7日13:30、19:00、NAC, Southam Hall、Ottawa
-Handel’s Messiah:12月17日、18日19:00、NAC Orchestra, Southam Hall https://nac-cna.ca/en/event/38429
トロント
TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA
-Holiday Pops: 12月10日、11日、14:00, 19:00、RTH
www.tso.ca/concerts-and-events/events/tso-holiday-pops
-Handels Messaiah: 12月16日、17日19 :30、12月20日、19 :30、21日15 :00、RTH
www.tso.ca/concerts-and-events/events/messiah-25
永田社中:(和太鼓)Nagata Shachu, https://nagatashachu.com/
-コンサート:Oto no Nami、12月6日20:00、Harbourfront Centre Theatre,Fleck (231 Queens Quay West, M5J 2G8トロント ON) https://harbourfrontcentre.com/event/oto-no-nami-sound-waves/
講座、講習、ワークショップ
和太鼓:Stephen Chan onikenbai.mtl@gmail.com, www.instagram.com/onikenbai.mtl
AU PAPIER JAPONAIS:店舗のみ営業、火曜‐土曜11:00-17:00、APJ www.aupapierjaponais.com/index.php
宮本食品店:日曜ワークショップ:すし、味噌造り、練切菓子、抹茶、https://miyamotomontreal.com/ MF
日本の踊り:こまちモンレアル、練習の問合せは、mtlkomachi@gmail.com/ 514-886-8129
三味線ワークショップ:JacintheのMTL三味線プロジェクト、問合せ先:Jacinthe info@mtlshamisenproject.com/
茶道裏千家淡交会モントリオール協会:chadomontreal@hotmail.com/
-小西真美子(宗真)指導、許状取次可(初級から上級)、市内、ウエストアイランド教室、514-630-0260 mamikoni54@hotmail.com/
-クーパー達子(宗立):全級、昼間、夜間、514-934-0410
古流松藤会: kazuko.dorangeville@gmail.com
草月流いけばな清美会:連絡先:Alain Carriere, Alain.carriere@hotmail.com
桃扇書道教室(JCCCM):師範シマード桃扇(美紀子)
水曜:10:00‐12:00 ラブレックホール
土曜:10:00‐12:00 地下集会室
tosen.shodo@gmail.com/ 514-298-4966
書道教室(NDG)有元合歓
稽古日:月曜日13:30-16:30 (月3回)連絡先:arimotoakiko@gmail.com
和田翠苑書道教室:LaSalle、ダウンタウン教室。和田扶美、514-750-3543、438−939−5643 info@japaneseshodo.com/ www.japaneseshodo.com/
間由加里陶器アトリエ:陶器ワークショップ、ギフトの注文承りなど。Studio Pottery Hazama, 7255 Rue Alexandre #103, Montreal, QC H2R 2Y9、514-483-4547 www.potteryhazama.com
Makiko Hicher:陶器制作、www.facebook.com/makikohicher/
ORIGAMI MONTREAL:問合せ:origami@sympatico.ca/
LANGUAGE TEA TIME:NUMA INSTITUTE、月曜—仏語、木曜‐英語、水曜‐日本語、15:30-17:30。
武道
志道館柔道クラブ:中村浩之指導、毎日、全クラスを指導 http://shidokanjc.ca/?lang=en
CLUB JUDO METROPOLITAN INC:http://club.judo.com/
CLUB DE JUDO HAKUDOKAN INC: http://judohakudokan.com/
マギル剣道クラブ:Christian D’Orangevilleほか指導 https://mcgillkendoclub.wordpress.com/
モントリオール剣道クラブ:戸井田健寿七段ほか、指導 www.montrealkendoclub.com/index.php?l=en
志道館剣道・合気道クラブ:www.shidokanmontreal.ca/
市外
HEATHER MIDORI YAMADA: www.ARTyamada.com/
JSS ONLINE PROGRAM:https://jss.ca/en/services/programs/online-programs/
映画
モントリオールの映画館、上映作品の情報:
www.cinemaclock.com/qc/montreal/
https://hotdocs.ca/festivals/hot-docs-festival
Cinéma Public: Casa d’Italia, 505 Jean-Talon E. https://cinemapublic.ca/?gad_source=1&gad_campaignid=13288483102&gclid=EAIaIQobChMI9NGjytrCkAMVuUhHAR3r3DDWEAAYASAAEgI9VfD_BwE
MONTREAL INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL(RIDM):国際ドキュメンタリーフィルムフェスティバル、11月20日‐30日。https://ridm.ca/en
トロント
Cine FAM-Women of Colours: 11月6日‐8日、https://cinefam.ca/
JFT Theater:国際交流基金による日本映画の配信が無料で行われています。フランス語字幕の映画もあります。https://en.jff.jpf.go.jp/
イベント会場
AGO Art Gallery of Ontario, 317 Dundas St. W.
APJ Au Papier Japonais, 24 Av. Fairmount O., 514-276-6853
AQHP Agora de l’Assemblée nationale du Québec Hôtel du Parlement、1045, rue des Parlementaires, Québec
BCH Bourgie Concert Hall, 1339 Sherbrooke W.
BDM Biodome of Montreal, 4777 Pierre-de Coubertin
BNM Basilique Notre-Dame de Montréal, 110 Notre-Dame W.
CCI Centre Cinéma Imperial, 1430 Rue de Bleury
CCL Centre Communautaire de Loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, 1700 Atateken
CI Casa d’Italia, 505 Jean-Talon E.
CQ Cinémathéque Québécoise, 335 boul. De Maisonnneuve est
DZB Dazibao, 5455 de Gaspé Ave., suite 109 (GF)
IM Insectarium, 4581 rue Sherbrooke E.
JCCC Japanese Canadian Cultural Centre, 6 Sakura Way, Toronto
JCCCM Japanese Canadian Cultural Centre of Montreal, 8155 Rousselot Street, 514-728-1996
JFT The Japan Foundation, Toronto, 2 Bloor St. E., 3rd Floor of Hudson Bay Centre, suite 300, 418-782-2277
LC La Cenne, 7755 boul. Saint-Laurent, suite 300
LN Le National, 1220 Ste-Catherine E, 514-845-2014, http://lenational.ca
MAC Museum of Contemporary Arts, address →PVM
MCC Monkland Community Centre, 4410 West Hill, NDG
MBG Montreal Botanical Garden, 4101 Sherbrooke E., Japanese Pavilion, 514-872-0607 pavillon_japonais@ville.montreal.qc.ca.
MCSM McCord Stewart Museum, 690 Sherbrooke St.W., 514-861-6701
MF Miyamoto Foods, 382 Victoria, 514-481-1952
MMFA Montreal Museum of Fine Arts, 1410 Sherbrooke W.
MSM Maison symphonique de Montréal, 1600 St-Urbain
NAC National Arts Centre, 53 Elgin, Ottawa, 613-947-7000 ext. 565, 1-888-991-2787
NGC National Gallery of Canada, 380 Sussex Dr., Ottawa, 613-234-6306
OAG Ontario Art Gallery, 50 Mackenzie King Bridge, Ottawa
OSM Orchestre symphonique de Montréal, 260 Maisonneuve W., 514-842-9951, www.osm.ca
PAC Pointe-à-Callière, 350 Place Royale
PDA Place des Arts, 175 Ste-Catherine W., 514-842-9951, www.pda.qc.ca
PDC palais des congrès de Montréal1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle
PHIC PHI Centre, 451 & 465 rue Saint-Jean
PRT Planetarium Rio Tinto Alcan, 4801 Pierre-de Coubertin
PVM Place Ville Marie
ROM Royal Ontario Museum, 100 Queen’s Park, Toronto, 416-586-8000, www.rom.on
RTH Roy Thompson Hall, 60 Simco St., Toronto
SJO Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal, 3800 Queen Mary Rd.
SPF Studio Pottery Hazama, 7255 Rue Alexandre #103, Montreal, QC H2R 2Y9
SWP Salle Wilfrid Pelletier, PDA
TM Thèatre Maisonneuve, PDA
YW YWCA Westmount, 4585 Sherbrooke W.