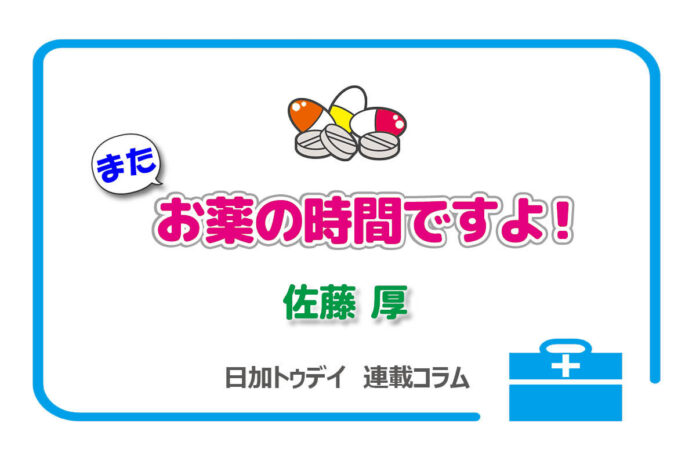コロナウイルスのパンデミック前は、いわゆるアンチワクチン派において、いかなる予防接種をためらう声も少なくありませんでした。しかしコロナを経験した今、社会全体で疾患の発症と重症化を防ぐ予防接種の価値が再認識されています。
薬局でも、最近はインフルエンザやコロナウイルスワクチンはもとより、肺炎球菌、RSV(RSウイルス感染症)、帯状疱疹、破傷風といった様々なワクチンについての相談が目に見えて増えています。そして、予防接種への前向きな流れは若年層でも加速しており、その代表格がヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンです。
HPVとは、200種類以上の型があるウイルスで、主に性的接触(性器同士・口と性器・性器周囲の肌と肌の密接な接触を含む)で感染します。特に高リスク型(例:16型・18型)は子宮頸がん、肛門がん、陰茎がん、陰唇・膣がん、そして男女共通の咽頭がんの原因となります。一方で低リスク型(例:6型・11型)は命に関わることは少ないものの、性器いぼ(尖圭コンジローマ)の主な原因です。多くの感染例は数か月〜1年ほどで免疫の働きにより自然に排除されますが、一部は粘膜に潜んで持続感染し、時間をかけて細胞に変化を起こすことがあります。
厚生労働省の資料によると、日本では子宮頸がんが年間約1万人発症し約2,900人が亡くなっており、若い女性の患者さんが増えているのも心配な点です。G7の中で日本の罹患率は最も高く、カナダのおよそ3倍と言われます。背景には、思春期から若年期のうちに、ウイルスに暴露される前にワクチンで体を守る仕組みや、早期発見の仕組みが十分に行き届いていないことが挙げられます。
ブリティッシュコロンビア(BC)州では、学校での定期接種(原則グレード6)を中心に、薬局やパブリックヘルスユニットなどでの接種機会と多言語の情報を提供、そして子宮頸がん検診(PAPテスト)が一貫して進められてきました。BC州では2008年にグレード6の女子から公費接種が開始され、2017年には男子にも適応を拡大することで思春期に入る前の年齢での幅広い予防を継続的に行ってきました。
そして、2025年7月からはHPVワクチン公費プログラムは大きく拡充されました。従来は9〜14歳が2回、15歳以上は3回(免疫不全は年齢に関係なく3回)、公費負担は19歳未満で開始し26歳未満で完了という公費負担条件がありましたが、新制度では9〜20歳が1回、21〜45歳が2回(免疫不全やHIV陽性は3回)へと簡略化。公費負担は19〜26歳の全員に広がり、さらに27〜45歳でもHIV陽性や、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、ノンバイナリー、クエスチョニング、Two-Spiritを自認する方は公費接種の対象となりました。これに加えて、コルポスコピー(拡大鏡で膣や子宮頸部を詳しく観察する検査)後の治療を受けた方は年齢に関係なく3回の公費接種対象に加わりました。このように接種対象が拡大されたことは、単なる条件の緩和ではなく、性別や年齢、背景の違いにかかわらず公平にワクチンを届けようとする社会的な取り組みであり、多様性と包括性を尊重する医療政策の象徴的な一歩と言えるでしょう。
日本では、2013年に定期接種が始まった直後、接種後の痛みや運動障害といった有害作用に関する報道で社会不安が拡大し、厚生労働省が異例の積極的勧奨の差し控えを決定したことで、接種率は急落しました。その結果、思春期に接種機会を逃した1990年代後半から2000年代生まれの世代が、HPVの大きな影響を受けています。HPVワクチンは感染前の接種が最も有効なため、この空白世代では将来の子宮頸がんリスク増加が懸念されています。2022年には積極的勧奨が再開されましたが、9年に渡り根付いた不信を払拭するには、正確な情報提供と、安心して接種を選べる環境づくりが不可欠と言えます。
HPVワクチンは、この18年間で大きく進化してきました。初期のワクチンは、子宮頸がんの主要な原因である16型・18型に加え、尖圭コンジローマの原因となる6型・11型を予防し、発がんリスクの約70%をカバーしていました。その後、ワクチンの改良により、現在主流の9価ワクチンでは、追加のハイリスク型(31・33・45・52・58型)を含む計9種類を対象にできるようになり、子宮頸がん原因の約90%を防げるまでに進化しています。加えて、接種世代を長期的に追跡した研究では、前がん病変や子宮頸がんの発症が実際に減少していることも証明されており、HPVワクチンは理論的な予防から、実際に効果が確認された予防へと新たな地位を築いています。
最近の薬局では、これまでよりも幅広い年齢の方にHPVワクチン接種を行なっています。公費接種の対象となる方に限らず、子宮頸がんのリスクがある方は、医師と相談しながら接種を検討することが望ましいでしょう。自己負担の場合は1本あたり約200ドル(薬局によって異なる)と安価ではありませんが、正確な情報に基づき、信頼できる医療者と相談することで、皆さんのライフステージに応じた適切な判断をしていただければ幸いです。
参考リンク:
Government of British Columbia
https://news.gov.bc.ca/releases/2025HLTH0076-000739
HealthLinkBC
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/human-papillomavirus-hpv-vaccine
国立がん研究センター がん情報サービス
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/17_cervix_uteri.html
*薬や薬局に関する一般的な質問・疑問等があれば、いつでも編集部にご連絡ください。編集部連絡先: contact@japancanadatoday.ca
佐藤厚(さとう・あつし)
新潟県出身。薬剤師(日本・カナダ)。 2008年よりLondon Drugsで薬局薬剤師。国際渡航医学会の医療職認定を取得し、トラベルクリニック担当。 糖尿病指導士。禁煙指導士。現在、UBCのFlex PharmDプログラムの学生として、学位取得に励む日々を送っている。 趣味はテニスとスキー(腰痛と要相談)
お薬についての質問や相談はこちらからお願い致します。https://forms.gle/Y4GtmkXQJ8vKB4MHA
全ての「また お薬の時間ですよ」はこちらからご覧いただけます。前身の「お薬の時間ですよ」はこちらから。