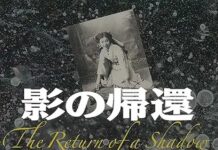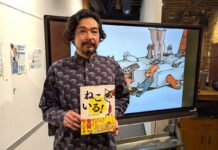初めての長編映画が、海外の舞台で静かに歩き出した。東京・渋谷の再開発を背景に、家族の関係と都市の変化を重ねた映画「見はらし世代(Brand New Landscape)」を手がけたのは、27歳の団塚唯我(だんづか・ゆいが)監督。23歳で脚本を書き始めたというこの作品は、「第78回カンヌ国際映画祭」監督週間に選出され、日本人として史上最年少、26歳での参加となった。
ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー市で開催された「バンクーバー国際映画祭(VIFF)」(2025年10月2日~12日)では北米プレミア作品(日加トゥデイ・メディアパートナー)として上映された。
日本での公開(10月10日)で多忙な中、オンラインで団塚監督に話を聞いた。
変わりゆく東京と、家族のかたち
再開発が進む渋谷を舞台に、離れて暮らす父と子どもたちの変化を描いた映画「見はらし世代」。ランドスケープデザイナーの父は仕事に没頭し、家族との関係は長く途絶えていた。ある日、父と再会した姉弟は、変わりゆく街の風景の中でそれぞれの記憶や思いと向き合う。
この作品は監督自身の体験に根ざしている。「もともと家族に対する違和感みたいなものがあって。僕は東京出身なんですが、東京の変わっていく街並みに対しても同じように違和感があったんです」と話す。
「家族という小さいコミュニティと、都市っていうすごい大きな枠組みって、真逆にあるようで、でも自分の中ではどこかで重なった瞬間がありました」。変わりゆく街と家族を対比させる発想は、都市に生まれ育った監督ならではの視点だ。

息子の蓮が渋谷で胡蝶蘭(コチョウラン)の配送運転手として働く設定については、「胡蝶蘭の配達ドライバーは低所得の仕事だけれど、高級品を扱うことで富裕層の空間に一瞬アクセスできる。都市の中で階層がすれ違う、その違和感を描きたかった」と語る。
映画との出会いは大学生の春休み
団塚監督が映画に出会ったのは大学時代。春休みに借りたDVDをきっかけに、「自分ならこう撮りたい」という発想が自然と芽生えた。当時通っていたのは、映像とは関係のない慶應義塾大学環境情報学部。YouTubeなどで独学を始めたあとに大学を退学し、映画美学校へ。短編作品を通じて現場での手法を学んだ。
「(映画を作り始めた当時は)18歳、19歳ぐらいのときで、何でもできると思っていた。今の自分だったら踏み出せなかったと思う」と振り返る。両親がデザイン関係の仕事をしていたことも創作の原動力となった。「何か作ることに対しての心理的ハードルが少なかった」と団塚監督。
その後、短編「遠くへいきたいわ」で注目され、出会ったスタッフや関係者との縁が今回の長編制作の道を開いた。
俳優の感覚を生かす現場作り
撮影では、脚本よりも現場で生まれる俳優の感覚や空気を大切にした。「間を詰めてほしいとか、リズム良くしてほしいとか、そういうことは言わなかったですね。むしろ言わないというか、(間は)取れたら取っていいし、取らなくてもいい。そういう言い方をしていました」と語る。

「役者さんがトライできる環境をどう作るか。僕が『何秒空けてください』と言うより、その人が『これ以上しゃべりたくない』と思った間をそのまま受け止める方が自然だと思った」。
映画作りの過程については「スタッフがそれぞれの持ち味を生かしながら、かけ算のように作品ができあがっていく。その過程がおもしろい」と話す。幼少期から野球部に所属していた団塚監督は、チームで目標を共有しながら進める感覚が映画制作にも通じていると感じている。
終盤に描かれる父と弟の場面では、言葉を排し、表情や空気の揺らぎで関係の変化を描いた。「どうやったら関係が変わっていくか。そのきっかけを説明ではなく映像の中で見せたかった」。印象的な空気感に、家族の距離が静かに変わっていく瞬間がにじんでいた。
東京から海外へ、映画が旅をする
海外での活躍については、「映画だけが旅をしているようで光栄です」と語り、自らはバンクーバーを訪れることができなかったが、遠い地で自作が見られていることを喜んだ。
映画の舞台となった東京は、監督にとって特別な街。「東京に生まれ育った自分が撮った東京の話を、海外の人がどう感じるのかが楽しみです。今の日本の都市を見られる映画にもなっていると思うので、見終わったあとに自分の住む町を少し違う目で見てもらえたら」と語る。
家族という小さな共同体を通して、都市の変化や人の時間を描いた「見はらし世代」。日本では10月10日から全国で順次公開している。
見はらし世代(Brand New Landscape)https://miharashisedai.com/

(取材 田上麻里亜)
合わせて読みたい関連記事